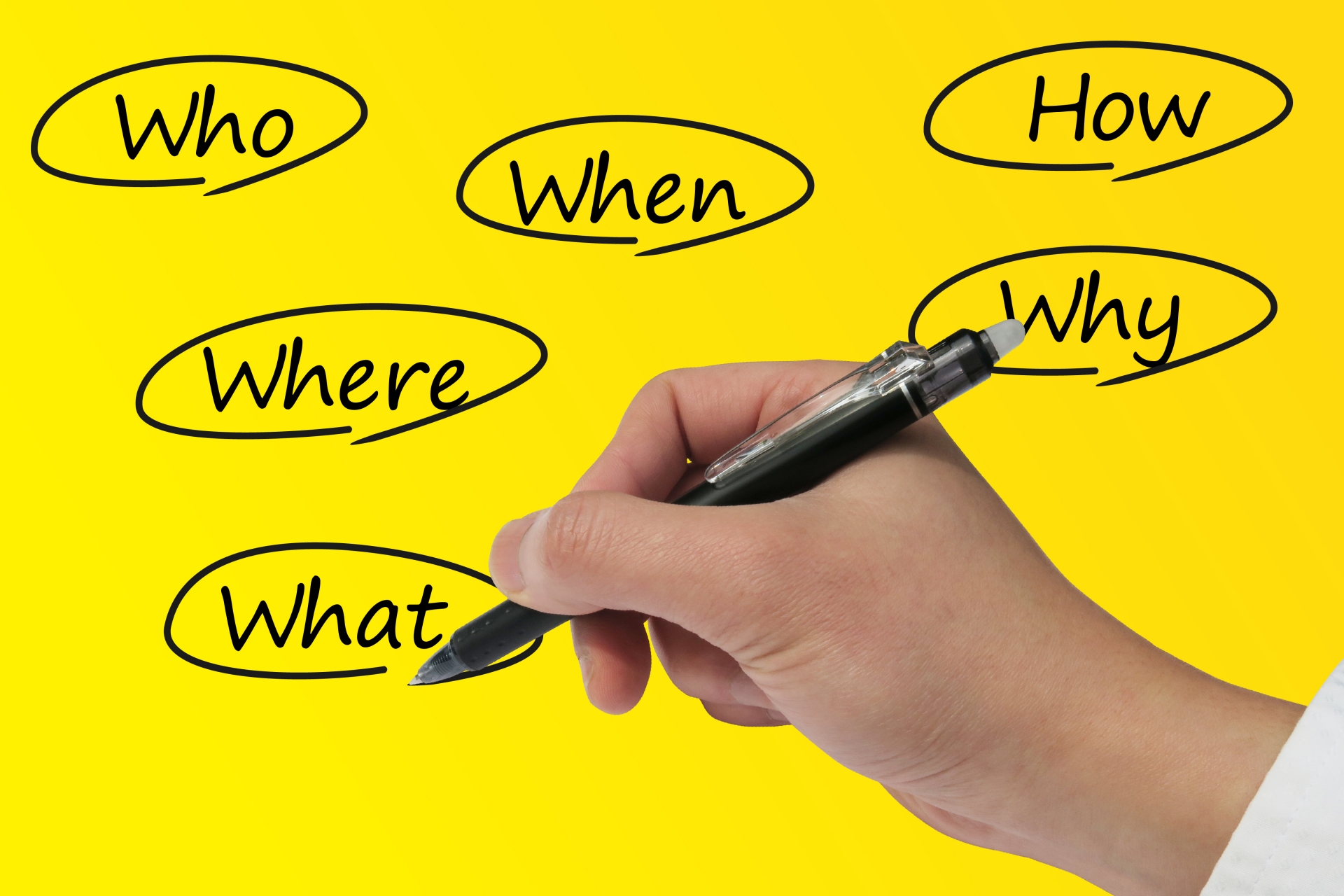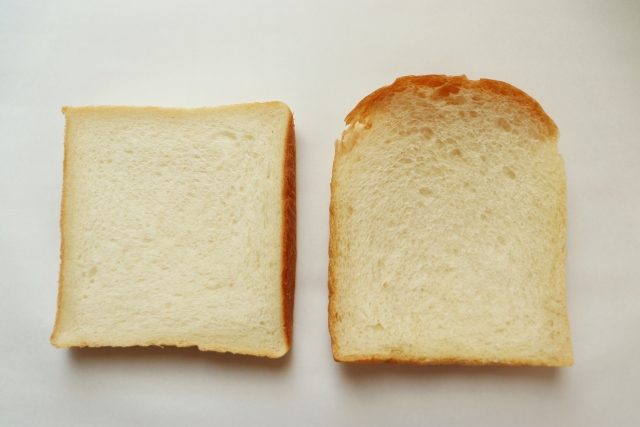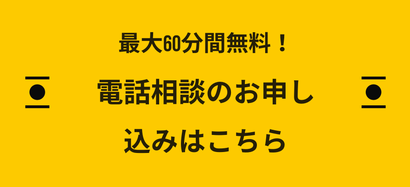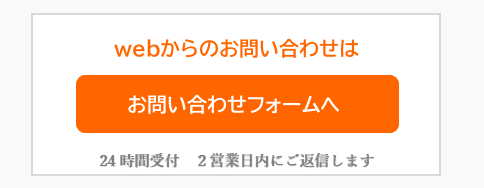日本政策金融公庫から融資を受けるときには金利を支払いますが、この金利にはどんな種類があって、どうやって決めているのでしょう?
また、金利をできるだけ低くする方法はあるのでしょうか?
ここでは、日本政策金融公庫の各種の金利と、金利の決め方、金利を低くする対策などについてご説明します。
日本政策金融公庫の金利の種類
日本政策金融公庫や銀行の金利には、大きくわけて「固定金利」と「変動金利」の2種類があり、それぞれの融資ごとにどちらかを適用するかが決まっています。
固定型金利とは、初回の返済~終了までの間、同じ利率が適用されるタイプの金利をいいます。
日本政策金融公庫では、ほとんどの融資がこのタイプの金利となります。
固定金利は、返済途中での金利変動の影響をうけないため、銀行としてはその分のリスクを織り込んで、変動型よりも高めに設定されていることがほとんどです。
また、「制度融資」(信用保証協会付融資)の金利も、多くがこのタイプに該当します。
変動型金利とは、一定の期間ごとに金利の利率を見直すタイプの金利をいいます。
日本政策金融公庫では、創業支援貸付利率特例制度など一部の融資がこれに該当します。
変動金利は、その時の情勢にあわせて金利の切り替えができるため、銀行側としてはリスクの回避がしやすい反面、借主にとっては返済の計画が立てにくいという面があります。
なお、「制度融資」の一部にも変動型の融資があります。
固定型金利と変動型金利の比較
| メリット | デメリット | |
| 固定型金利 | 長期の返済計画が立てやすい | 選んだ時期によっては、ずっと高い金利のままとなる |
| 変動型金利 | 金利の変動に対応できる | 金融情勢によっては高金利となる |
日本政策金融公庫の金利の種類と利率
日本政策金融公庫には、通常の企業向けの融資を取り扱う部門として、「国民生活事業」と「中小企業部門」の2つがありますが、いずれにおいてもほぼ同じ融資を取り扱っています。
この2つの部門の違いは、主に企業規模や融資額によるもので、小規模の企業については前者が、中規模の企業については後者が対応しています。
以下は、日本政策金融公庫の国民生活事業で取り扱う代表的な融資となります、
| 融資制度 | 対象者 | 融資上限額 | 金 利 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 一般貸付 | 事業を営む人 | 4,800万円 ※運転資金と設備資金を含む特定設備資金 7,200万円 |
【基準利率】 ※担保ありの場合
|
運転資金 5年以内 ※特に必要な場合7年(据置1年以内)設備資金 10年以内(据置2年以内) 特定設備資金 |
| 担保を不要とする融資 | 税務申告を2期以上行っている方 | 4,800万円 ※運転資金と設備資金を含む |
【基準利率】 2.06~2.55% |
各融資制度に定めるご返済期間以内
担 保:不要 |
| 新創業融資制度 | 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) | 【基準利率】 2.41~2.90% |
各種融資制度で定める返済期間以内
他1/10以上の自己資金が必要などの要件あり 無担保・無保証 |
| 創業支援貸付利率特例制度 | 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方 | 各融資制度に定める融資限度額 | 各融資制度定める率-0.3% | 各融資制度に定めるご返済期間以内
一部ご利用いただけない融資制度あり |
| 新規開業資金 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 【基準利率】 1.11~2.20% ※担保なしの場合 ただし、一定の要件に該当する場合は特別利率を適用 |
運転資金 7年以内(据置2年内)設備資金 20年以内(据置2年内) |
| 女性、若者/シニア起業家支援資金 | 女性または35歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 特別利率A 0.71~1.80% ※担保有の場合 ただし、一定の要件に該当する場合は特別利率を適用 |
運転資金 7年以内(据置2年内)設備資金 20年以内(据置2年内) |
| 再挑戦支援資金 | 新たに開業する方または開業後概ね7年以内の方で、一定要件に該当する方 | 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円) | 【基準利率】 1.11~2.20% ※担保有の場合ただし、一定の要件に該当する場合は特別利率を適用 |
運転資金 7年以内(据置2年内)設備資金 20年以内(据置2年内) |
| 新事業活動促進資金 | 「経営革新計画」の承認を受けた方や、新たに経営多角化・事業転換を図る方など一定要件に該当する方 | 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円) | 【基準利率】 1.11~2.20% ※担保有の場合ただし、一定の要件に該当する場合は特別利率を適用 |
運転資金 7年以内(据置2年内)設備資金 20年以内(据置2年内) |
| 中小企業経営力強化資金 | 外部専門家の指導や助言、または「中小企業の会計に関する基本要領」の適用などにより、経営力の強化を図る方 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 【基準利率】 1.11~2.20% ※担保有の場合ただし、一定の要件に該当する場合は「特別利率A」を適用 |
運転資金 7年以内(据置2年内)設備資金 20年以内(据置2年内) |
| 経営環境変化対応資金
(セーフティネット貸付) |
業況悪化により最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少しているなど、一定の要件に該当する方 | 4,800万円 | 【基準利率】 1.11~2.20% ※担保有の場合 |
運転資金: 8年以内(3年以内)
設備資金:15年以内(3年以内) |
| マル経融資(小規模事業者経営改善資金) | 商工会議所、商工会などの経営指導を受けていて、商工会議の推薦を受けた方 | 2,000万円 | 【特別利率F】1.21% | 運転資金: 7年以内(1年以内)
設備資金:10年以内(2年以内) 無担保・無保証人 |
| 挑戦支援資本強化特例制度 | 新規開業資金他一定の融資制度を利用される方で、地域経済の活性化にかかる事業を行うこと、所得税等を完納していることの要件を満たす方 | 4,000万円
ただし、一部のの融資制度に限り、別枠4,000万円 |
融資後1年ごとに、直近決算の業績に応じて、貸付期間ごとに3区分の利率が適用 | 5年1ヵ月以上15年以内(期限一括償還)
無担保・無保証人 四半期ごとの経営状況の報告等を含む特約を締結 |
| 経営者保証免除特例制度 | 一定の要件を満たす、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方 | 各融資制度に定める融資限度額 | 保証免除した貸付は、適用する融資制度の利率に0.2%が上乗せされます | 融資にあたり、経営者の保証が免除される |
| 新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が5%以上している人 | 8,000万円(別枠) | 【基準利率】 1.11~2.20% ※担保有の場合ただし、6,000万円を限度として融資後3年目まで 基準率-0.9%、4年目以降は基準利率 |
運転資金: 15年以内(5年以内)
設備資金:20年以内(5年以内) 無担保・無保証人 一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分について利子補給あり |
※ 2021.04.03現在
金利の決め方について
日本政策金融公庫で金利を決めるときには、次のような要素をもとに決定しています。
2 特別な条件の有無
3 担保・保証人の有無
4 融資の申込み額や返済の期間の長さ
5 借主の信用力
日本政策金融公庫では、融資の種類により適用される金利が決まっています。
通常は基準金利が適用されますが、マル経融資のように特別金利が適用されるものもあります。
日本政策金融公庫の融資では一定の要件を満たせる場合には、その条件に応じて金利が低くなる場合があります。
例えば、女性、若者/シニア起業家支援資金の場合は、通常は特別利率Aが適用されますが、技術・ノウハウ等に新規性がみられる方については特別利率A・B・Cのいずれかが適用されます。
日本政策金融公庫の融資では、原則として担保または保証人が必要となります。
ただし、新創業融資制度や担保を不要とする融資制度などを利用できる場合には、担保・保証が必要な融資についても、これを無担保・無保証または無担保で利用することができるようになります。
なお、この場合は、担保や保証が必要な場合より、金利が0.15~0.3%高くなります。
融資の金利は、申込額や返済期間の長さによっても影響をうけます。
一般的には、申込額が多い、返済期間が長いほど金利はその分高くなります。
金利は以上の要因の他、借主の信用力によっても変わります。
信用力が高いほど低い金利が適用されますが、この信用力はこれまでの返済の実績や債務者区分などにより決定されます。
「債務者区分」とは、金融庁が決めた借入れをしている企業のランクを財務内容にもとづいて決めたもので、次のように区分されています。
債務者区分
| 企業の状況 | |
| 正常先 | 経営・財務とも健全な企業 |
| 要注意先 | 財務状態が不安定で、今後注意を要する企業 |
| 要管理先 | 3ヶ月以上の長期延滞が発生しているなど、財務状態に問題を抱えている企業 |
| 破綻懸念先 | 財務状態が悪化しており、破綻の可能性が高い企業 |
| 実質破綻先 | 再建の見通しが立たず、破綻目前の企業 |
| 破綻先 | 破綻状態にある企業 |
この区分のランクが低い場合には、借入れそのものができなくなります。
参 考 債務者区分ついては「これで企業の運命が決まる!債務者区分とは?」を参照ください。
金利を引き下げる方法について
融資の金利は、以上のような基準によって決定されますが、次のことをすることで、ある程度、金利を下げられる可能性があります。
2 信頼できる決算書を作成する
3 業績の進捗状況を定期的に報告する
4 特許や公的に認証を取得する
5 制度の高い事業計画書を提出する
金融機関が融資審査で重視するのは、「これまでの信用=返済の実績」です。
既存の融資の返済で、支払いの遅れや延滞などがなく計画通りに返済が行われている場合には、日本政策金融公庫もこれを高く評価します。
会社の財務内容の把握をするために、最も重要なのが「決算書」です。
但し、同じ決算書であっても、単に税務申告用に作られているものよりかは、金融機関の融資に配慮した内容の決算書である方が評価が上がります。
融資に配慮した決算書のポイントとしては、次のようなものがあります。
| ● 決算書の提出期限内に提出されたものであること。 ● 過年度分の未払いの税金がないこと。 ● 「仮払い金など」などの未精算科目がないこと。 ● 会社から代表者への多額の貸付金がないこと。 ● 売掛金と買掛金のバランスがとれていること。 ● 売掛金について複数年にわたる未回収金がないこと。 ● 累積の赤字がないこと。 ● 連続した赤字や債務超過でないこと。 など |
参 考 「融資を引き出す決算の6つのポイント」についてはこちら
定期的に自社の財務内容や事業の進捗についての報告をすることは、金融機関との関係性をよくするとともに、企業の評価UPにつながります。
報告の期間としては、できれば3ヶ月ごとが望ましいですが、それが難しい場合には6ヶ月ごとでも構いません。
なお、銀行は毎年の決算終了後に決算書の提出を求めてくることがありますが、言われてから出すのでなく、その前に進んで提出することが必要です。
特許や国・都道府県の認証などを取得している場合には、その経営が高く評価されますので、これらを取得している場合には金利の引き下げに影響を及ぼす一因となります。
これは3の業績の進捗状況の報告にも通じるものですが、精度と実現可能性の高い事業計画書を提出することにより、金融機関の信用を獲得することができます。
また、このような取り組みについては、金融庁も金融機関はこれを支援するべしとされていることから、金利の引き下げが期待できます。
信用保証料の決め方
信用保証協会付の融資や制度融資を利用する場合には、一定の手数料がかかります。
これを「信用保証料」といいます。
この保証料は、融資の金利とは別にかかるものなので、注意してください。
以前は、この保証料は保証金額にスライドする形で決められていましたが、現在では融資先の企業の財務内容や過去の返済実績などで決められています。
この決定の仕方を「スコアリング」といいます。
標準的なスコアリングの企業の保証料は「約1%」となっていますが、業績や返済実績の良い企業はこれよりも安く、そうでない企業では高くなります。
なお、一部の制度融資では、この保証料の一部を行政が補填したり、ケースによっては全額を免除している場合もあります。
まとめ
以上のように融資の金利は主に、融資の種類や担保の有無により大半は決まりますが、信用力などによっても変ってきます。
したがって、できるだけ融資の金利を引き下げたいとお考えの場合には、まずは「信用力の向上」ができないかについても検討するべきとなります。
119番資金調達NETでは、融資の申込みの以外にも、金利の引き下げや金融機関への信用力の改善のサポートを行っています。
また、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。
随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
※ こちらから電話できます。