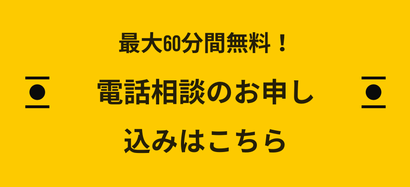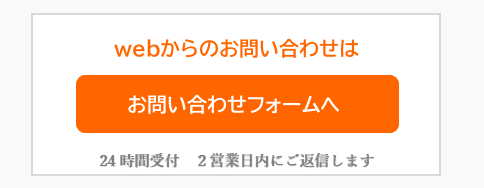皆さんは、日本政策金融公庫の創業融資で、「絶対に注意しなければならないこと」があるというのをご存知でしょうか?
もし、そのうちの一つにでも該当すると、ほぼ必ずといってよいほど融資に失敗してしまいます。
しかし、これだけ重要にも関わらず、意外と多くの方がこのことを知らずに申し込んでしまっています。
なので、ここではその危険度ごとの要注意ポイントについてご説明します。
危険度ごとの創業融資NGポイント
あると致命的な項目(💀💀💀 失敗率95%~)
◆ 家賃や公共料金等の支払がキチンとできていない
◆ 信用情報がブラックになっている
◆ 代位弁済をされている

自己資金が不足している、その出所を説明できない。
日本政策金融公庫の新創業融資制度では、原則、「創業にかかる経費の1/10以上の自己資金」が必要とされています。
例えば、500万円の融資を申込むのであれば、最低でも50万円以上の自己資金が必要となるわけです。
そのため、自己資金額がこの最低限の割合に届かない場合には、融資はお断りとなってしまいます。
参 考 新創業融資制度の使い方完全解説!自己資金がなくても0K?制度融資との関係は?
また、必要なだけの自己資金が用意できているとしても、その資金が借りたものだったり、その出どころを説明できない場合にも、融資はほぼ否決となります。
通常、次のようなものは、自己資金として認められません。
■ どのように貯めたかの経緯が不明な資金
■ 現金で保有している資金(いわゆる「タンス預金」)

家賃や公共料金等の支払いがキチンとできていない
創業融資では、家賃や公共料金といった定期的に支払うものについて、未払いや支払いの遅れがある場合にはほぼ融資は難しくなってしまいます。
このように定期的に支払うもので、審査でチェックされるものには次のようなものがあります。
■ 住宅ローン・その他ローンの支払い
■ 税金(自宅所有者については、固定資産税も対象)
なお、これらの支払いの遅れ等は、引き落しの通帳の履歴を確認する、支払い済みの領収控え(いわゆる耳)などにより確認がされます。
これは今後、融資の返済をしてもらう金融機関にとっては当然ともいえることなのですが、意外と知らない人が多いようです。
たった1回ぐらいの遅れなら大丈夫だろうと思う人も多いですが、ほぼ融資はアウトとなります。

信用情報がブラックになっている
日本政策金融公庫では、申込人の信用情報を確認しています。
以前は「日本政策金融公庫では信用情報の確認をしていない」などという話もありましたが、現在はシッカリと行われています。
もし、その情報の中にローンの支払の遅れや未払いといった情報が登録されている場合には、融資は不可となります。
なお、信用情報の代表的な記号の見方は、以下をご参考ください。
P 請求の一部の入金あり
A 契約者都合による未入金
B 契約者都合ではない未入金
C 未入金であり原因不明
- 請求も入金もなし
また、信用情報が抹消されるのは、遅れ等があったときからではなく、「正常な支払いを再開したとき、または事故となった原因が解消された時」から一定の期間を経過したときとなります。
参 考 : 信用情報の記号の味方については、 融資にどう影響する? 信用情報のウソ、ホント。
したがって、これらの状態が解消できていない方については、何年たっても信用情報が抹消されないことに注意してください。
代位弁済をされている
「代位弁済」とは、信用保証協会の債務を弁済できないときに、同協会が金融機関に代わって弁済をする手続きをいいます。
この手続きがされた場合には、それ以降、借主は信用保証協会に対して返済をすることになりますが、この代位弁済中の人は日本政策金融公庫からも融資を受けることができません。
また、代位弁済を受けた人の連帯保証人でまだ弁済が済んでいない方についても、本人と同様に融資が受けられなくなります。

かなり危険な項目(💀💀 失敗率70%~)
◆ 事業経験がほとんどない
◆ 求められた資料を用意しない
◆ 決算書を作成・提出していない ※ 1期経過の場合
◆ 面談で担当官とケンカ
これらの項目のいずれかに該当する場合は、必ず融資に失敗するというわけではありませんが、かなり失敗の確率が高くなります。
また、リカバリーしようとしてもできないものがほとんどなので、このような項目を作らないようにしてください。

必要な許認可が取れていない
営業をするために何らかの許認可が必要となる場合には、あらかじめその許認可を取得、もしくは融資が下りるまでの間に取得しておく必要があります。
もし、これが取得できない場合には融資は不可となりますが、融資の決定後に許可が出るような場合には、その間、融資の実行が保留となります。
なお、日本政策金融公庫では、飲食店の営業許可については例外的に、事前に取得できていなくとも融資が下りる取り扱いとなっています。

事業経験がほとんどない
新創業融資制度では、「一定の事業経験があること」が要件となっています。
日本政策金融公庫では、この事業経験がかなり重要視されており、事業経験がない、もしくは極端に少ない場合には、融資はかなり難しくなります。
なお、この経験についてはどのくらいあればよいのかが明確にされていませんが、できれば3年以上はあった方がよいでしょう。
参 考 : 事業経験の少ない人は、創業融資の事業経験がなくても、こうしてカバーできる!を参照。
また、アルバイトの経験も内容によっては事業経験として認めてもらえますが、経営に関係のない単純労働だけの場合などには難しくなります。

求められた資料を用意しない
新創業融資制度の審査では、決められた必要書類以外についても提出を求められることがあります。
例えば、次にあげるものなどは必須とはされていませんが、ケースによっては提出を求められることがあります。
■ 納税証明
■ 前職の給与明細
資料を求められたときにこれを提出できないのは、大きな評価のマイナスとなります。
特に事業計画書の不提出は、間違いなく融資のお断りとなりますが、必要な項目の未記入の場合も大きな減点の対象となります。
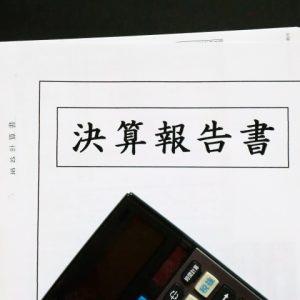
決算書を作成・提出していない
新創業融資制度は、開業前や開業直後の方だけでなく、開業後2期を過ぎるまでの方も利用することができます。
そのため、中には申込時に1期を過ぎている方もいますが、このような方は1期目の決算書や確定申告書を提出しなければなりません。
にもかかわらず、この決算書等を提出できないような場合には、それが融資審査で大きな不利となります。
面談で担当官とケンカ
日本政策金融公庫の審査では、その過程で担当者との面談が行われますが、たまに担当者と口論をしてしまう方がいます。
確かに、担当者の中には「チョット、あまりじゃないか?」という人もいますが、だからといってケンカや口論をしてしまうと、ほぼ融資は通らなくなってしまいます。
もし、その場でわからないことがある場合でも、「調べたうえで改めて報告します」といえば特に問題にはならないので、いい加減な回答をしないようにご注意ください。
できるだけなくしたい項目(💀 失敗率50%~)
◆ 事業計画書の内容がずさん
◆ 申込額が過大である
◆ 最近、日本政策金融公庫の融資に落ちている
多額な他人の連帯保証人となっている
申込本人に信用情報上の問題がない場合でも、その人が多額の連帯保証人となっている場合には、潜在的な負債を負っているとみられるため、融資が通りくくなります。
事業計画書の内容がずさん
事業計画書の内容に未記入部分がある、間違っている、誤字脱字が多いなどの場合には、融資の評価を下げることになります。
特に、事業計画書に関する以下の点については間違いが多いため、注意が必要です。
| ■ 貸借対照表の左右の金額があっていない ■ 売上げについての根拠が記載されていない ■ 返済できるだけの利益が確保できていない |
申込額が過大である
融資の申込額を決めるときに、何の根拠もなく自分が欲しい金額を申し込む方が多いですが、このような無計画な内容では、融資のお断りまたは大幅な減額となります。
一般的な融資の申込額の目安は「必要な設備の購入額+3~4ヶ月分の運転資金-自己資金額」となります。
したがって、申込み額の中に不必要な設備が入っていないか、期間の長すぎる運転資金を申し込んでいないかなどについて注意してください。
最近、日本政策金融公庫の融資に落ちている
日本政策金融公庫では、一度、融資の申込みで失敗すると、すぐに再申し込みをしても成功しないケースが多く、再度の申込みで成功するためは、一般的に6ヶ月以上の時間が必要とされています。
一度目の融資に失敗しても、それが短期間で修正が可能なものならば、もっと短い期間での申込みでもOKとなることもありますが、最近に失敗しているようなケースでは融資が出るまで時間がかかると思った方がよいでしょう。
参 考 : 融資お断りからの復活事例については、 私は日本政策金融公庫に融資を断られた。そして、こうして復活した!を参照
以外な盲点! 創業融資の失敗例

日本政策金融公庫の創業融資については、これら以外にも気をつけたい点があります。
特に、フランチャイズでの創業の場合には、次のことに注意してください。
フランチャイザーに問題がある場合(実例あり)
フランチャイズに加盟して開業する場合には、申込み本人だけでなくその加盟元(フランチャイザー)についても審査が行われます。
そのため、申込人に問題がなくとも、加盟するフランチャイザーの経営や財務内容に問題がある場合には、申込人についても融資が出ないことになってしまいます。
なぜなら、融資の審査ではフランチャイザーとフランチャイジーは一体の経営と見られるからです。
実際にあった例
飲食店のフランチャイズに加盟して開業を予定していたAさんは、自己資金も十分にあり、飲食業の経歴も豊富な方でしたが、日本政策金融公庫の新創業融資制度に申し込んだところ、完全なお断りとなってしまいました。
納得のいかないAさんが何度も担当者に確認したところ、担当者からは
「審査の結果、Aさん自体には何の問題もありませんでした。しかし、加盟するフランチャイザーが以前に当行から受けた融資を返済しておらず、いわゆるブラックとなっているので、あなたにも融資ができません。」
との回答がされました。
このことはあまり知られいませんが、融資の審査ではこのような取り扱いとなってしまうため、フランチャイズの選定の際には、できれば決算書などでその会社の財務内容なども確認しておいた方がよいでしょう。
まとめ
一部では「簡単に借りられる」などといわれている日本政策金融公庫の創業融資ですが、実際にはこれだけの気をつけなければならないポイントがあります。
特にはじめにあげた
◆ 自己資金が不足している、資金の出所を説明できない
◆ 家賃や公共料金等の支払がキチンとできていない
◆ 信用情報がブラックになっている
◆ 代位弁済をされている
などの項目に該当する場合には、ほぼ融資はムリとなってしまうのであらかじめ十分な確認をし、もし、いずれかに該当する場合には、それが解消できるまで申込みを待つといったことも考えた方がよいでしょう。
なお、119番資金調達NETでは、創業融資をご希望の方について事業プランのアドバイス、創業計画書の作成・面談などのサポートを行っています。
「自分のケースではどうなるか聞きたい」などといったチョットしたことでも、無料でご質問を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。