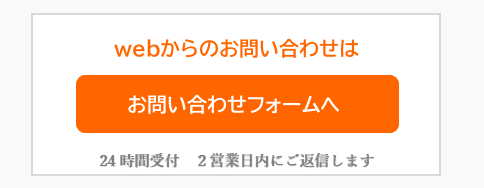これから飲食店の開業をされる中には
「少しでも、経費を減らしたい。」
「国の支援があったら利用したい」
と思っている方は多いのではないでしょうか?
そんな方にピッタリなのが「補助金や助成金」です。
「でも、普通の飲食店では補助金や助成金は使えないのでは?」とお考えのあなた。
飲食店でも補助金や助成金をもらうことはできます。
けれど、補助金や助成金の申請には多くの手続きが必要なため、キチンと仕組みを理解しておかないと「手間だけがかかってこれだけ?」ということになりかねません。
また、補助事業を行う場合に立て替えが必要となる資金の対策も考える必要があります。
この記事では、補助金と助成金の違いや、これらを受給するためのポイント、補助金に適した融資について解説いたします。
補助金と助成金の基礎知識
補助金や助成金の申請を正しく行うには、これらについてその違いや特徴を理解しておくことが前提となります。
補助金・助成金の種類
補助金・助成金は、これらを明確に区別する法律や規則はありませんが、一般的には次のように分類されています。
● 補助金……厚生労働省以外の省庁(経済産業省など)や民間団体が管轄・主催するもの
● 助成金……厚生労働省が人の雇用や労働環境の改善に関して支給するもの
ただし、企業がこの厚生労働省の助成金等を受給するためには、雇用保険への加入が要件となっていることが多いため、助成金の申請をするのならば、まずは雇用保険へ加入することをお勧めします。
補助金・助成金の特徴
【共 通】補助金・助成金ともに返済不要でもらえるお金である。
【助成金】厚生労働省が行う助成金は、要件に該当し申請すれば誰でも受給できる。
ただし、内容は人の雇用や退職、制度の改善に関するものがほとんど。
また、雇用保険への加入が原則として必要。
【補助金】補助金は、一定の審査に合格しなければ受給できない。(コンテスト形式)
物や設備などの購入費用に関するものが多い。
【その他】補助金等としてもらった給付金は原則、非課税扱いとなる。
融資を活用して補助金を最大限もらう方法
補助金や助成金は確かに魅力的ではありますが、一つだけ使いづらい部分があります。
それは「経費先払い、補助金後支給」だということです。
これは「補助金や助成金をもらうためには、経費にかかる必要額を自分で立て替え払いしなければならない」ということを意味します。
仮に、補助上限額300万円、補助割合1/3の補助金を最大まで利用するためには、
300万円×3=900万円を補助事業資金として、支払う必要があります。
しかし、資金繰りの余裕のない会社にとって、これだけの金額を受給前に支払うのは大きな負担となります。
そのため、せっかくよい技術やプランがあっても、先立つ資金ががないために、補助金や助成金の申し込みをあきらめざるを得ないというケースも少なくありません。
しかし、自分の手持ちのお金を使わずに、補助金等を最大限までもらう方法があります。
それが「融資を受けたお金で、補助事業に必要なものを購入する」というやり方です。
具体的には、以下のような感じとなります。
| ● 助成金 - 人の雇用や人件費を融資の資金で支払う ● 補助金 ― 物の購入の経費を融資の資金で支払う |
このように、先に融資で得た資金を使って補助金等に必要な費用を支払えば、手持ちの現金を減らさずに補助事業を行うことができます。
例)上限額200万円、助成率1/2という補助金の場合
● もし上限額200万円をもらうためには?
⇩
● 先に400万円の支出が必要
⇩
● 400万円について先に融資を獲得しておく
⇩
● この資金を使って補助事業を実行
⇩
● 審査に通れば後から200万円が戻ってくる
日本政策金融公庫では、補助金申請と組みあわせて利用できる融資として、次のようなものがあります。
● 創業者向け ➡ 「新規開業・スタートアップ支援資金」
● 女性・若者・シニア向け ➡ 「女性、若者/シニア起業家支援資金」
● 飲食業向け ➡ 「企業活力強化資金」
このように両者をうまく組み合わせることにより、手持ちの現預金を使わず融資の資金で、大きな額の補助金にエントリーすることができます。
飲食店でも申し込める助成金と補助金
飲食店でも申し込み可能な助成金や補助金には、次のようなものがあります。
中小企業新事業進出補助金
「中小企業新事業進出補助金」は、事業再構築補助金が第13回公募(2024年度)をもって終了することを受けて、2025年度から開始される予定の補助金です。
補助対象者 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等
補助上限額 従業員数に応じて2,500万~7,000万円 ※補助下限750万円
補助率 1/2
その他 ・新製品(又は新サービス)を新規顧客に提供する新たな挑戦であること
・付加価値額の年平均成長率が+4.0%以上増加などの要件あり
・建物費、システム構築費、外注費、広告宣伝費など(人件費は対象外)
ものづくり補助金(製品・サービス高付加価値化枠)
「ものづくり補助金」は、中小企業・小規模事業者が生産性向上に貢献できる革新的な新製品・新サービス開発のための設備投資やシステム導入を行う際に活用できる補助金です。
製造業に限らず、商業・サービス業など幅広い業種が対象となります。
補助対象者 革新的な新製品・新サービスの開発に取り組む事業者
補助上限額 従業員数に応じて750万~2,500万円
補助率 中小企業:1/2、小規模事業者:2/3
その他 ・生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発のための設備投資
・設備投資費、システム構築費、試作開発費、外注費など(人件費は対象外)
・公募期間は2025 年 2 月 14 日~4 月 25 日
中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)
「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」は、人手不足解消のため、IoTやロボットなどを導入する際の経費の一部を補助する補助金です。
補助対象者 人手不足の状態にある中小企業等
補助上限額 従業員数に応じて200万~1,500万円
補助率 中小企業:1/2
その他 ・付加価値額向上に効果的な汎用製品をカタログから選択
・IoTやロボットなどの購入費
・公募期間は2025年1月30日~2025年3月31日
・他に「一般型」あり」
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。
補助対象者 最近3カ月間の月平均値が10%以上減少しているなどの要件を満たす事業者
補助率 休業手当または教育訓練実施の場合の賃金相当額の2/3 ※8,635円が
教育訓練を実施したときの加算(額) 1,200円/人/日
補助率 中小企業:1/2
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、特定の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成される制度です。
補助対象者 ハローワーク等の紹介により、高年齢者や障害者等などを雇用する事業者
補助額 60~240万円 ※短時間労働者以外
その他 ・支給額は特定求職者の種類により異なる
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」は、就業規則等にもとづき、パートなどの有期雇用労働者等を正社員にした場合に助成される制度です。
補助対象者 就業規則等にもとづき有期雇用労働者等を正社員にする事業者
補助額 20~80万円/人 特別加算20万円 or 40万円
その他 ・正社員となる方の就業形態により金額が変わります。
トライアル雇用助成金(一般コース)
「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」、就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用する事業主に対して助成する制度です。
補助対象者 週の労働時間30時間以上の者をトライアル雇用する事業者
補助額 4万円/人 ※最長3ヶ月
補助金の交付の流れ
一般的な補助金の「申請」〜「交付」までのスケジュールは、次のようになっています。
■ 申 請
■ 審 査
■ 交付決定
■ 実績報告
■ 検査・清算
■ 確定通知
■ 交付(入金)
なお、助成金のうち厚生労働省が行うものなどについては、
「要件の準備」➡「申請」➡「審査」➡「支給」
のように手続きが簡単なものもあります。
補助金・助成金の申請に関する注意点
補助金や助成金の申請・受給をする場合には、次の点に注意が必要です。
補助事業にかかる費用は、事業者が全額を立替え払いしなければならない
補助金や助成金は、「先払い、あと支給」が原則です。
そのため、事業主の方は、補助事業にかかる経費の全額を一時的にですが、すべて立て替え払いできるだけの資金力が必要となります。
受給までの時間が長い
補助金や助成金は、申請からお金が振り込まれるまで半年~1年近くの時間がかかることがあります。
とくに、補助金では、この期間が長くなるものが多いといえます。
そのため、このことをはじめに計画に入れて資金繰りをしないと「補助金をもらえるまで資金が続かない」などとなってしまうため注意が必要です。
必ず予定額がもらえるわけではない
補助金の申請をして審査を通ると、申請者の方には「交付決定書」により、補助額が通知されます。
これを見て、必ずその額がもらえると勘違いされる方がいますが、そういうわけではありません。
この額はあくまで提出した計画に基づいて暫定的に算定されたものであり、最終的な額は清算後の「確定通知」に記載された額となります。
もし、補助事業中に、事業の一部中止があったり、補助金要領で定められた使い方をしていない場合などには、補助額が減額されます。
このように「交付決定額」=「支給額」ではないため、金額が減額される可能性があることを理解しておく必要があります。
内容や要件が頻繁に変わる。申請期間が短いものが多い。
補助金は同じ制度が数年にわたって複数回実施されることもありますが、1回切りでなくなってしまうものもあります。
また、定期的に実施されているものであっても、その内容は頻繁に変更されます。
とくに補助金については、短期間で応募が締め切られてしまうものも多いため、募集が始まってから申し込んだのでは、資料を作る時間がないということになりがちです。
したがって、補助金の申請を確実にするには、できるだけ早く情報収集をし、事前に募集期間をつかんで早めに準備しておく必要があります。
補助金や助成金を返還しなければならない場合もある。
補助金や助成金は、原則、返還の必要がないものですが、「不正受給」をしてそれが発覚した場合には、その一部または全額を返還しなければなりません。
例えば、本来しなければならないことをしていなかったり、一定の基準を満たしていないにもかかわらず、これを満たしたように申告する行為は「不正受給」とみなされ、助成金や補助金の返還だけでなく、刑事罰の対象となることもあります。
また、補助金によっては「その補助金をもらって行った事業により、補助額を超える利益が出た場合にはその一部を返還しなければならない」と定められているような場合もあります。
国の検査の対象となることがある
補助金や助成金を受給したときには、会計検査院の検査対象となることがあります。
これにより不正が見つかった場合は、不正部分に関する補助金等を返還しなければならないだけでなく、税務上の加算や修正申告の必要が生じるため、大きな時間と資金のロスとなります。
まとめ
補助金・助成金には、「返還不要の資金が手に入る」、「技術やアイデアが認められる」という大きなメリットがあります。
しかし、「立て替え払いで一時的に資金繰りが厳しくなる」、「必ずしも全額が支給されるわけではない」などのデメリットも存在します。
もし、手元資金が十分でない場合には、それにあわせて融資を受けておくことで、資金不足への対策となります。
119番資金調達NETでは、創業融資や補助金、それに関する融資のサポートの他、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。
随時、初回相談は無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
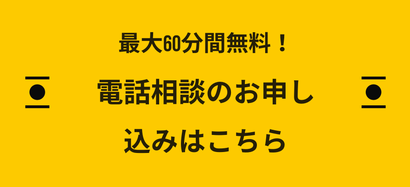
※ こちらから電話できます。