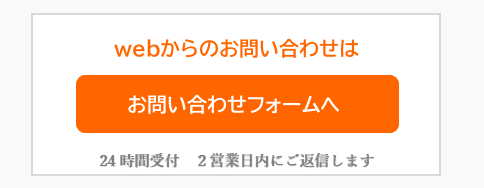「自己資金も揃った」、「場所も確保できた」
さあ、融資を申し込もう!とお考えの方
チョット、待ってください。もしあなたが「とりあえず、空欄を埋めればよいだろう。」という感覚で事業計画書を作ろうと考えているのであれば、まずはここに書かれていることを読んでからにしてください。
なぜなら、創業融資の事業計画書には、計画を組み立てるための順序があるからです。
そもそも、事業計画書は、用紙の順番通りに書き込めば計画が作れるという仕組みにはなっていません。
なので、この順番を無視して取り掛かってしまうと、かなりの確率で「つじつまが合わない」、「こんなはずじゃなかった!」ということになってしまいます。
そうならないためにも、まずはここでお伝えするステップでチェックをしてから、計画書の作成に臨んでいただきたいと思います。
目次
STEP1: 融資に必要な条件を満たせているか?
創業者の方が日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」を利用しようとする際には、まずは、この融資制度で定められている条件を満たしていなければなりません。
しかし、本当に融資を成功させたいと考えているのなら、これだけでなく、「融資を利用するうえで、当然満たしていなければならない条件」があります。
前者を「(特定の)融資制度の利用条件」とするならば、後者は「すべての融資に共通する基本的条件」といえます。
つまり、融資で希望の額を獲得するには「融資制度の利用条件」だけでなく、「融資の基本的条件」も満たせていなければならないということになります。
よく、融資の申し込みで「あっさりとお断りされた」、「1円も融資が出なかった」という方を見かけますが、そのほとんどはこの「融資の基本的条件」を満たせていないケースがほとんどです。
「融資制度の利用条件」と「融資の基本的条件」
「融資制度の利用条件」と「融資の基本的条件」を「新規開業・スタートアップ支援資金」の例で説明すると、次のようになります。
<融資制度の利用条件>
| ● 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方であること ● 無担保・無保証で利用したい場合には、 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方であること |
<融資の基本的条件>
| ● これから行う事業について、ある程度の実務経歴があること(できれば3年以上) ● 電気、ガス、水道料金、家賃、固定資産税、各種ローンのように毎月定期的に支払う ものについて支払い遅れや未納がないこと ● 税金(主に住民税や市民税)の納付が条件となっている場合に、これらの納付漏れが ないこと ● 個人情報に問題がないこと、過去の未納や支払い遅れの情報がすべての情報登録機関 に登録されていないこと ● 法人で申込む場合は法人登記が、個人の場合には開業届の提出が済んでいること ● テナントを借りて営業する場合は、借りる物件のめどが立っていること ※ ただし、申し込み時点では、契約までしている必要はなし ● ある程度の自己資金があること |
最低でも、これらの条件は満たせている必要があり、これらのどれか一つにでも引っかかってしまうと、簡単にお断りとなってしまいます。
しかし、少なくない数の方が、はじめの利用条件だけを見て「自分は大丈夫!」と思ってしまうため、融資が出ない、大きく減額されるということになってしまいます。
融資の基本的条件が満たせていない場合には、原則、お断り、よくて減額となりますので、これらをすべて満たせていない場合には、問題が解決するまで申し込みはやめた方がよいといえます。
まだ、自己資金は必要なのか?
「融資の利用条件」を見て、「新規開業・スタートアップ支援資金」の利用に、自己資金は不要ではないかと思った方もいらっしゃるかと思います。
しかし、結論からいえば、
「現在でも、ある程度の自己資金は必要」
といえます。
確かに、日本政策金融公庫の創業融資制度が、以前の「新創業融資制度」から現在の「新規開業・スタートアップ支援資金」に変わったことにより、それまで必要とされてきた「1/10以上の自己資金の保有」は申込条件から削除されました。
けれど、これはあくまでも「申込条件からなくなった」=「自己資金なしでも申し込めるようになった」ということであり、「自己資金がなくとも融資が出る」ではありません。
この点については、日本政策金融公庫の担当者にヒアリングしたときの記事「公庫担当者から聞いた。「新規開業支援資金」の80%の人が知らない事実」に詳しく紹介していますが、
「日本政策金融公庫では、現在でも融資審査において自己資金の有無を重視している」
といえます。
そのため、表面的な条件だけを見て「自己資金がなくても融資が出る」と考えてしまうと、大きな失敗のもととなってしまうので、やはり申し込みにはある程度の自己資金を用意しておく必要があります。
STEP2: 借入額と資金のバランスを考える
事業計画を作る前に必要なのが、資金のバランスを見積もっておくということです。
よくあるパターンとして、まず先に
・必要と思われる設備額や運転資金を積み上げた額を計算する
・導き出された額から自己資金額を差し引いた残りを融資申込額にする
というやり方で計画を作るというパターンがあります。
しかし、この方法で計画を作ると、たいてい本来借りられる実力以上の金額となってしまいます。
なぜなら、見積もりの段階で「あれもこれもと自分の欲しいものを入れてしまう」からです。
それがすべて合理的に説明のつくものであれば問題ありませんが、ほとんどのケースで「資金額が多すぎ」と判断されて減額されることになります。
これをはじめに考えておかないと
・実力的に借りられる金額以上の申込額となってしまう
・途中で計画上の内容が破綻し、大幅なやり直しが必要となってしまう
ということになります。
ではどうすればよいかといえば、「融資額と返済可能額」、「運転資金の月数」、「自己資金と融資申込額」のバランスを考えたうえで、実際の計画を作るということになります。
STEP3: 融資申込額と返済可能額を考える
事業計画書のバランスを考えるうえで必要なのが「融資申込額と返済可能額」です。
当然ですが、日本政策金融公庫は返済をしてもらうことを前提に融資をしますので、申込額が返済可能だろうと見込まれる額を超えている場合には、お断り、もしくは減額となってしまいます。
そのため、これから見込める利益(事業計画書上の利益)を正確に把握し、それに見合った申込額とする必要があります。
見込める利益(事業計画書上の返済可能利益)
では、見込める利益(事業計画書上の利益)はどのように算定すればよいかについてですが、融資の返済に充てることのできる額は、次の式で計算することができます。
「売り上げから原価と経費を差し引いて残った額 + 購入した設備の減価償却額」
たとえば、売り上げ1,000万円/年、経費800万円/年であれば、残る利益は200万円/年となります。
また、購入する設備の減価償却費が30万円/年ならば、年間の返済に充てられる利益額は230万円/年となります。
融資の申込額
返済可能利益の計算ができたら、次にこれにもとづいて理論上いくらまでなら融資を申し込めるかを計算します。
上の例で、融資の返済期間を7年として申し込む場合は、
230万円/年×7年=1,410万円
が計算上の申し込める額となります。
しかし、もし、年間の利益が150万円しかない計画ならば、(150万円+30万円)×7年=1,260万円となってしまうため、計画もこの規模に合わせて見直す必要が出てきます。
申込額の見込みはこのようにして算出することがスタートとなりますが、そのためには元となる事業計画書においてしっかりとした売り上げと経費の見込を立てることが非常に重要となります。
運転資金の月数を考える
通常の創業融資の申し込みでは、設備資金と運転資金の両方が必要となりますが、運転資金や設備資金としては、次のものが該当します。
【運転資金の例】
● 家 賃(仲介手数料、礼金を含む)
● 仕入代 人件費 水道光熱費 交通費
● リース料 宣伝広告費 雑 費 など
【設備資金の例】
● 保証金または敷金 内・外装費
● 厨房設備 車の購入費 など
融資の申込みでは「運転資金は〇〇円以下でなくてはならない。」とか「設備資金はこうでなければダメ」といった決まりはないのですが、常識的に考えた場合の限度の目安というものは存在します。
その目安とは、
「運転資金の申し込みについては、原則、3ヶ月分~4ヶ月分」
です。
なぜ、運転資金の限度がこうなるのかといえば、それは掛取引をした場合の回収期間がこの程度であるということにあります。
創業者の方は仕入れ先に対する信用がないため、取引きは基本的に現金払いとなりますが、一方、販売については相手が一般消費者でなければ売掛けとなるのが普通です。
そして、売掛金の回収条件が1ヶ月の場合には、実際に代金が入金されるのは1~2ヶ月後となり、回収条件が2ヶ月の場合には、代金の入金は2~3ヶ月後となります。
しかし、一般的にはこれ以上の期間となることは少ないため、通常は約3ヶ月分の建替え資金があれば、資金繰りは回せることになります。
このような理由から、金融機関の側としても、妥当な運転資金の目安は3~4ヶ月分と考えており、そのため申込額もこれに合わせた方がよいということになります。
では、設備資金についても同じような目安があるのかといえば、こちらについてはそういうものはなく、「営業に必要なものであれば申し込んでOK」ということになっています。
したがって、融資申込全体の目安は、以下のようになります。
融資申込全体のバランス
(1ヶ月分の運転資金 ✖ 3~4ケ月分) + (適正な設備の資金)
STEP4: 費用の根拠を精査する
事業計画書では売り上げと経費、利益の見込を出して、返済に問題がないことを示しますが、それらの見込みが根拠のないものであるならば、融資はお断りや減額となってしまいます。
そのため、これらの項目がいかに実現可能性のあるものであるかを、計画上で示さなければならないこととなります。
売り上げ
売り上げの根拠の作り方については「金融機関も認めた!創業融資を引き出す売上げ計画の作り方」の記事に詳細に説明していますが、具体的には次の3つを計画で示すようにします。
| 売上げの金額・・・いくらの売り上げを予定しているのか? 売上げの妥当性・・・その売上げで返済ができるだけの利益は出るのか? 売上げの根拠・・・売り上げの根拠は何か?信用できるものなのか? |
たとえば、飲食店場合の売り上げは、次の式で求めることができます。
客単価 × 席 数 × 回転数
そして、あなたが想定する計画の内容が客単価 (2,500円)、 席数(15席)、 回転数(1.2回転)である場合の売り上げの見込みは以下の金額となります。
客単価 (2,500円)× 席 数(15席) × 回転数(1.2回転) = 45,000円/日
このうち席数は店舗の構造により、また、回転数は同業者のデータにもとづき説明できますが、客単価については店それぞれで異なるため、なぜこの金額になるのかを具体的に説明する必要があります。
この場合に最も簡単にできるのが、「自店のメニューを使った方法」です。
仮に、メニュー上で「お通し 300円」、「ビール 500円」、「低価格料理 300円」、「通常価格料理 600円」となっているのであれば
300円 + 500円×2杯 + 300円×2品 + 600×1品 = 2,500円/人
のように説明することができます。
このように売り上げの見積もりは、何となくこれぐらいとするのではなく、その中身に説得力のある根拠が求められます。
運転資金
運転資金とは、設備資金以外のすべての経費のことをいいます。
運転資金については、見積もりがあるものについては見積書をつけて金額の根拠としますが、見積書のないものについては、自分でその根拠を算定します。
なお、水道光熱費など具体的な計算が難しいものについては、ネットで簡易的に計算ができるサイトがありますのでこれらを使っても構いません。また、20万円以下の備品等については、アマゾンなどで商品価格がわかるページをプリントアウトしたものを見積もりとして使ってもOKです。
例
人件費
@1,000円/h × 7h × 18日 = 126,000円
交通費
A @500円(片道) × 2 × 18日 = 18,000円/月
B @300円(片道) × 2 × 18日 = 10,800円/月 など
設備資金
設備資金については、購入予定の設備や内装費などについて、販売業者から正式な見積もりをもらった金額を根拠とします。
ただし、あまり高額でないもの(10万円未満)については、運転資金の場合と同様、ネットの商品価格がわかるページを見積書として利用しても構いません。
申込前に購入したものに注意
以上の計算をするうえで注意しなければならないのが、
「申込前に購入し、支払ったものは融資申し込みの対象にならない。」
というルールです。
このルールはすべての融資で共通しているのですが、これを知らずに支払い済みのものを申し込んで、結果的に融資額が大幅に少なくなってしまったという方がいます。
たとえば、令和7年4月1日にテナントの契約金100万円と内装工事の手付金50万円を支払い、令和7年4月10日に融資を申し込んだ場合は、支払済みのの150万円については融資を申し込めません。
この点を理解した上で運転資金や設備資金の計算をしないと、後になって「これは対象にならない」となってしまう可能性があります。
STEP5: 自己資金との申込額のバランスを考える
最後に注意しなければならないのが、「自己資金と申込額のバランス」についてです。
前述したように新たな「新規開業・スタートアップ支援資金」では、自己資金は不要とされていますが、これはあくまでも申し込みの条件であり、融資の審査では自己資金があった方が絶対に有利となります。
というよりも、自己資金がまったくない状況での申し込みは、かなり厳しいものとなります。
申込額と自己資金はどの程度のバランスがあればよいかにつき、明確な決まりはありませんが、一般的には3~4倍程度が妥当とされています。
自己資金 1 : 融資申込額 3~4倍
したがって、自己資金が300万円の場合は、1,000万円程度が妥当な申込額となります。
ここまでの説明で
STEP3では、「売上げから原価と経費を差引いて残った額 + 設備の減価償却額」
STEP4では、(1ヶ月分の運転資金 ✖ 3~4ケ月分) + (適正な設備の資金)
と説明しました。
これらによれば、少し大きめの規模の開業ならば1,000万円を軽く超えてしまうこととなります。
しかし実際には、最後の自己資金とのバランスの目安を考慮する必要があるため、それなりに大きな自己資金がある方でないと、1,000万円を超える融資の申し込みは難しいということになります。
(1ヶ月分の運転資金 ✖ 3~4ケ月分)+(適正な設備の資金) ≒ 自己資金の3~4ヶ月分
そのため、はじめにこれらのことを意識して、自分の計算した見込額がこの範囲内で収まっているかを見ながら、計画を作っていく必要があります。
まとめ
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」で開業資金を借りる場合には、事業計画書の提出が必須となりますが、計画を作るときにいきなり勢いだけで始めてしまうと、後になって問題の多い内容となってしまいます。
日本政策金融公庫に受け入れられやすく、できるだけ多くの額の融資を引き出すには、あらかじめ審査のポイントを知り、順序に従った手順で作ることで、融資の出やすい、やり直しのない計画を作ることができます。
119番資金調達NETでは、融資の申込みの他、事業計画書の作成の代行を割安な金額でお手伝いしています。
なお、119番資金調達NETでは、新規開業資金の申込みのサポートの他、、このブログではご紹介していないテクニックや注意点についても、直接、その方の状況にあわせてアドバイスしています。
随時、初回の相談無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
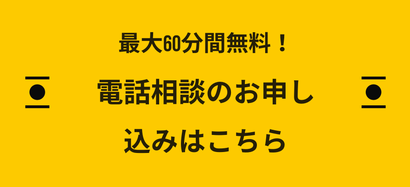
※ こちらから電話できます。